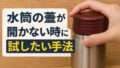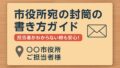「800字の作文って、どうやって書き始めればいいの?」
就職試験や志望理由書、小論文などで課される「800字作文」に、初めて挑戦する人も多いのではないでしょうか。
この記事では、800字作文の基本的な構成や段落の分け方、さらにすぐに使える例文も紹介します。初めての人でもスムーズに書き出せるよう、やさしく解説していきます!
800字作文とは?
800字作文は、就職試験や推薦入試、小論文などで頻繁に出題される文章形式の一つです。800字という文字数は、短すぎず長すぎない絶妙な長さであり、筆者の論理的思考力、表現力、構成力などが総合的に問われる点で非常にバランスの取れた形式だと言えます。また、限られた字数の中で自身の意見や体験を簡潔に伝える必要があるため、文章を「どうまとめるか」「どこに重点を置くか」という編集力も重要になります。
実際の試験では、テーマに沿った自己体験や意見を根拠づけて書くことが求められるケースが多く、曖昧な記述や抽象的な表現は評価されにくくなります。そのため、読み手に明確に意図が伝わる構成と、無駄を省いたスッキリとした文章展開が必須です。作文に慣れていない人にとってはハードルが高く感じられるかもしれませんが、基本的な構成を押さえておけば、誰でも書き進めやすくなります。
初めてでも安心!800字作文の基本構成
導入(100〜150字程度)
テーマの背景や、自分がそのテーマに興味を持ったきっかけを書きましょう。読者の興味を引きつけつつ、自然に本論につなげる役割を果たします。導入部分で自分の体験や価値観に少し触れると、読者に親近感を与えることができます。また、「なぜそのテーマを選んだのか」を具体的に述べることで、文章全体に一貫性が生まれます。
例:「私は中学生のころから読書が好きで、多くの本に触れてきました。物語の世界に没頭する中で、自分の価値観や考え方が大きく広がったと感じています。その中で、特に印象に残った一冊があります。」
本論(500〜550字程度)
メインの主張や経験、考えを詳しく述べます。体験談 → 課題 → 解決策 → 得た学び、という流れにすると、論理的で説得力のある内容になります。
話の流れが途中で脱線しないように注意しながら、なるべく具体的な出来事や心情の変化を描写することが大切です。
実際にどんな行動をとったのか、誰と関わったのかといった情報も加えると、読者の理解が深まります。
また、課題や困難をどう受け止めたかを明確にし、そのうえで乗り越えた過程を丁寧に描写すると、文章に厚みが出ます。
結論(100〜150字程度)
本論のまとめと、自分の気づきや将来への抱負を簡潔に述べましょう。感謝の気持ちを添えると、丁寧な印象に仕上がります。ここでは、作文全体で伝えたかったメッセージを再確認する場でもあります。学びを一言で言い表し、それを今後どのように活かしていきたいかを示すと、締めくくりとして効果的です。
例:「この経験を通して、目標に向かって努力することの大切さを実感しました。今後もこの姿勢を忘れず、社会でも活かしていきたいと考えています。そして、自分を支えてくれた周囲の人たちへの感謝の気持ちを、これからの行動で示していきたいと思います。」
作文を書く前に押さえるべきポイント
テーマをよく読む
「あなたの考えを述べなさい」→このような指示がある場合は、自分自身の意見や価値観をはっきりと示すことが求められます。テーマに対する考えを明確にし、その根拠を具体的な体験や観察に基づいて論じると説得力が増します。
「体験を通して」→この場合は、あなたが実際に経験した出来事や、そこから得た気づき・成長を中心に構成する必要があります。客観的な事実と自分の内面の変化をセットで語ることで、読み手に共感を与えやすくなります。また、体験の内容が日常的なものであっても、自分なりの視点や学びを加えることで印象的な文章になります。
構成メモを作る
文章の流れをメモで整理すると、書き出しや展開がスムーズになります。例えば、「導入→体験→課題→解決→まとめ」というように、段階的に構成を描いておくと全体の流れがはっきりし、途中で脱線するのを防げます。時間配分や段落構成の目安にもなるため、限られた試験時間内で安定した文章が書けるようになります。
さらに、メモを見直すことで、論理の抜けや表現の重複にも気づきやすくなり、より完成度の高い作文につながります。
例文で学ぶ!800字作文の実例
テーマ:「困難を乗り越えた経験」
私が困難を感じたのは高校2年生の時の文化祭準備でした。私はクラスの実行委員を務めており、企画の立案からスケジュール管理、当日の進行までを担う立場にありました。しかし、準備が思うように進まず、役割分担の偏りや意見の食い違いから、メンバー間には不協和音が生まれ、緊張が走りました。中にはやる気を失いかけて消極的になる生徒もおり、クラス全体の士気は日に日に低下していきました。この状況に対して、私は強い危機感を抱きました。
このままでは文化祭当日に間に合わないという焦りと責任感から、私はクラス全員が参加できる話し合いの場を設けることを提案しました。話し合いでは、お互いの意見を冷静に聞くことを重視し、どんな立場の生徒でも自由に発言できる雰囲気づくりを心がけました。特に、発言に対する否定的な反応を排除することで、意見が言いやすい空気を作ることを意識しました。時間をかけて何度も話し合いを重ねるうちに、それぞれの考えや想いが共有され、次第に共通の目標を意識するようになり、自然と協力体制が生まれていきました。
その結果、出し物は無事に完成し、本番当日は笑顔あふれるステージを披露することができました。観客の拍手に包まれながら達成感に満ちたその瞬間、私たちは本当の意味で「ひとつのチーム」になれたと実感しました。この経験を通して、チームワークの難しさと、相互理解を深める対話の大切さを身をもって学びました。意見が異なるからこそ、話し合う意味があり、理解し合う努力が信頼関係や人間関係を築くのだと改めて感じました。
今後もチームで物事を進める際には、相手の立場や思いを尊重することを意識し、建設的な話し合いを大切にしていきたいと考えています。意見が分かれたり衝突が起こったとしても、互いの考えに耳を傾ける姿勢を忘れず、冷静に対応することが重要です。必要に応じて自分の考えを見直す柔軟性も持ちながら、よりよい解決策を模索していきたいと思います。
(※この例文で813字です)
よくある失敗とその対策
文字数が足りない/オーバーする
伝えたいことが整理されていないと、文字数の調整が難しくなります。文字数が足りない場合は、具体的なエピソードや背景の補足を追加し、内容に厚みを持たせましょう。例えば、出来事の前後関係や心情の変化などを描写すると、自然に文字数が増えて説得力も高まります。
一方、文字数がオーバーしてしまう場合は、似たような内容が重複していないか見直しましょう。同じことを繰り返していないか、不要な形容詞や冗長な表現がないかをチェックし、簡潔で要点の伝わる表現に修正することが重要です。限られた字数の中で伝える力を養うことが、作文力向上の鍵となります。
話があちこちに飛ぶ
文章の構成が曖昧な場合、読み手にとって話の筋が見えにくくなります。基本の構成である「導入→本論→結論」の流れを常に意識し、書き出す前に構成メモを用意することが効果的です。
各段落で伝えるべきポイントをあらかじめ決めておくことで、主題に沿った論理的な展開が可能になります。また、段落内でも時系列や原因と結果の関係を意識すると、文章にまとまりが出ます。脱線しそうになったら、構成メモに立ち返る習慣をつけましょう。
主張がぼやけている
読後に伝わるメッセージが曖昧では、印象に残りにくい作文になってしまいます。結論では、自分の考えや学びを「だから私は〜と考えます」などの明確な言い回しで締めくくることが大切です。
また、文章全体を通して主張が一貫していることが求められます。途中で意見がぶれていないか、自分の立場が曖昧になっていないかを見直しながら書き進めましょう。主張を支える根拠やエピソードがしっかりしていれば、文章全体の説得力も自然と高まります。
まとめ
800字作文は、明確な構成と具体的な体験を通して、自分の考えを伝えることがカギとなります。例文や構成を参考にしながら、まずは書いてみることが大切です。
繰り返し練習すれば、自然と読みやすく説得力のある文章が書けるようになります。構成メモからスタートし、自信を持って取り組んでいきましょう!